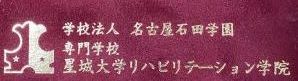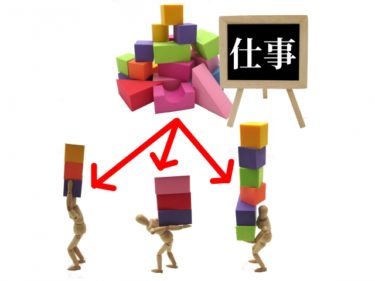自己紹介と入会のきっかけ
はじめまして。岩田裕太郎と申します。
初めての記事で不手際が多々あるかと思いますがご容赦下さい。
初回の記事では…
- 自己紹介
- 入会理由、なぜNOVASTだったのか
を書いていきたいと思います。宜しくお願いします。
自己紹介
私は平成22年の3月に星城大学リハビリテーション学院を卒業し、同年の4月に名古屋市内の維持期病院へ就職しました。職場の先輩からの紹介をきっかけにNOVASTを知り、平成27年11月から第3期生としてNOVASTストレッチのカリキュラムを受け、平成28年4月にNOVASTトレーナーの認定を受けました。
私の職場では主に脳神経疾患を罹患された70~90歳前後の入院患者さんに対するQOL(生活の質)向上を目指したアプローチが中心となります。
維持期の特徴としましては、身体機能改善の見込みはとてもわずかであること、主介護者も高齢者であることが多いこと、病歴が長く本当の意味でのリハビリテーションの意欲が乏しいこと(マッサージやおしゃべりを目的とされる方が多い)などがあげられます。
対するアプローチとしては、身体機能評価を詰めて今出せる身体能力のピークを探ること、次期転院・入所先に合わせた身体能力を獲得するための動作指導、補助具の選定、環境整備、介護者への提案と指導、疼痛緩和、また、入院生活を少しでも楽しく過ごせるような提案や介入、あとおしゃべりなどが主になります。
入会理由、なぜNOVASTだったのか
私は自己紹介の中にあるように、卒業後すぐに維持期病院に就職し現在まで来ております。そのため、上記のような維持期・慢性期の患者さんに関しては現在までに約10年分の経験をしてきました。代わりに、身体機能の大きな改善やそれを起因とした身体能力の向上を経験する機会はほとんどありませんでした。急性期・回復期・維持期とも同じく患者さんのQOLの向上を目的として介入をしているといってもアプローチの内容は大きく異なることが多いのです。つまり、私は慢性期、維持期の理学療法士であって、急性期や回復期に関してはほぼ素人でした。
学生時代にあった理学療法士のイメージ、「機能改善→能力向上」、「疼痛の原因究明→解消」、「疼痛の予防」という部分に関する経験と自信は少なく、ちゃんと専門家としての知識や能力が自分にはあるのだろうかという不安感がいつもどこかにありました。何か技術を身につけたい、全身を万遍なくみれるような、まとまった知識を得たい。しかし、講習会は局所的な部位に対する限局した技術や知識ものが多く、また一つ一つが高い。どれを受講すればいいのかわからない。そんなこんなで目を通しはするものの受講には至りませんでした。
そんなある日、職場の先輩に紹介を受けてNOVASTの体験講習を受講する機会がありました。NOVASTでの講義の内容は主に基礎(解剖や機能解剖)から始まり、疼痛発生の原因と理屈、評価の方法、ストレッチや筋間・筋膜リリースを交えた徒手アプローチの方法、アフターフォローという流れで、それを半年にかけて全身を学んでいくことになります(体験では肩関節)。正に私が求めていたものであり、入会の意思はその日のうちに決まっていました。
入会のきっかけやNOVASTを選んだ理由は以上になりますが、入会してから得られたものはそれらの知識や技術だけではありませんでした。
NOVASTを紹介してくれた先輩は「理学療法士だからって病院で働くことがすべてじゃない。ここには理学療法士の経験や知識を生かして色々な働き方をしている人がたくさんいる。そういう人達と関りを持つのは自分の将来を考える上でもいいことだ。」とおっしゃっていました。
そうなんです。NOVASTには病院だけでない、様々な場所で活躍する療法士がいて、自分の知りえなかった様々な療法士の形を身近にみたり、話をきく機会を得ることができるんです。
今では維持期の経験しかないことに不安はありませんし、自信を持つこともできています。それはNOVASTで知識や技術が得られたことはもちろんですが、それ以上にそれらNOVAST会員の人たちとのかかわりを経て自分の中の「療法士」の枠を大きく広げられたことがとても強い要因だと考えております。
療法士にも様々な働き方があり、それに応じて必要な知識や技術も変化する。
私もそんな療法士の枠を広げる一人になれたら、それも面白いなと思っております。
以上です。これからも宜しくお願い致します。